 「はてしない物語」ミヒャエル・エンデ
「はてしない物語」ミヒャエル・エンデ
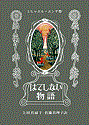 「はてしない物語」
「はてしない物語」
ミヒャエル・エンデ : 作 , 上田 真而子 , 佐藤 真理子 : 訳
ロスヴィタ・クヴァートフリーク : 装画
岩波書店 , 590p. , 1982年
ISBN : 9784001109818
私が初めて装丁の美しさに惹かれた本。そして、徹夜するほど時間を忘れて読んだ本は、
この「はてしない物語」でした。
小学三年生のとき、確か、長期休暇でも連休でも週末でもない、普通の日でした。
翌日の授業の内容は夢の彼方で、見事に覚えていません(O先生ごめんなさい)。
この本は、世界中で翻訳されているドイツ指折りのファンタジー作家、ミヒャエル・エンデの代表作。
80年代の人気映画『ネバーエンディングストーリー』の原作でもあります。
人気作で星の数ほどレビューがあることを幸い、物語の紹介は先達にお任せして、
今回は「児童文学として」より、「装丁」と「物語」とのリンクを「面白い!」と思ってくださる
方向きの、いつも以上に趣味に走った、ミーハー路線の内容でお送りします。
物語の紹介からは横道に逸れた回となりますが、もしよろしければお付き合いください。
現在、日本版の「はてしない物語」には三つの版があります。
一つ目は、今回の記事で最初に紹介した1982年発行の豪華版。
二つ目は、2000年に上下分冊で発行された文庫版。
三つ目は、2005年に刊行されたエンデ全集の第4巻と5巻(これも分冊)です。
「単行本は重くて疲れるし嵩張るから、文庫の方が好みだ。」という方は
結構多くいらっしゃいますし、それは通常好みの問題だと私も思います。
「文と絵が同じなら、どの版でも同じ。わざわざ高い本を選ばなくても良いだろう。」
…そう思われるのももっともなこと、無理もないことかもしれません。
けれど実は、特にこの「はてしない物語」においては、「本の装丁」そのものが大切な鍵。
読者が物語の世界を大きく膨らませるための、重要な鍵になっているのです。
物語の冒頭部分で、主人公のバスチアンは同級生から逃げて飛び込んだ古書店で
一冊の本と運命的な出会いをします。その時の様子を引用すると…。
バスチアンは本ととりあげると、ためつすがめつ眺めた。
表紙はあかがね色の絹で、動かすとほのかに光った。
パラパラとページをくってみると、中は二色刷りになっていた。
さし絵はないようだが、各章の始めにきれいな大きい飾り文字があった。
表紙をもう一度よく眺めてみると、二匹の蛇が描かれているのに気がついた。
一匹は明るく、一匹は暗く描かれ、それぞれ相手の尾を咬んで、楕円につながっていた。
そしてその円の中に、一風変わった飾り文字で題名が記されていた。
―――はてしない物語 と。
初めてこのシーンを読んだ時の驚きと心の震えを、私は今でも忘れることができません。
何故なら、「本の中の主人公が読んでいる本」が、今、自分の手の中にある本、そのものだったから。
それは、言葉にならない大きな感動でした。
本の装丁ひとつで、ここまで大きく感動を膨らませるものなのか。と、子供心に驚きました。
本の後ろに「本を作る人」を感じた、最初の一冊とも言えます。
ぜひ、一人でも多くの人にこのゾクッとするほどの幸せな驚きを感じてほしい。
だから、この「はてしない物語」は、ぜひ1982年発行の豪華版で読んでもらいたい。
あかがね色の、布張りの、二色刷りのこの版で読んでもらいたい!と、心の底から思います。
日本でこれほど長く、深くこの物語が愛され続けているのは、
お話の面白さも勿論ですが、この素晴らしい装丁の影響も大きいのではないでしょうか。
装丁といえば、「はてしない物語」は印刷もとても独特なのですが、これは精興社によるもの。
精興社は、百年近い歴史を持つ東京の印刷会社です。
「美しい本を手にしたければ、奥付に《精興社》とある本を探しなさい」
とは、大学の時にお世話になった、詩人でもあられた教授の言葉ですが、
精興社の本は本当に文字がきれいで、文字組も美しく、凛とした印象の本が多いです。
この本で使われているフォントはこの会社ならではの活版印刷の時代を思わせるものですが、
読みやすくも力強く、微妙なインクの濃度の変化が手仕事の温かみまで伝えてくれるようで、
それでいて一度読者が物語に集中すれば、さらりと文章に溶け込むしなやかさもあって…
まさに、「はてしない物語にはこの活字しかない!」と言いたくなるほどのぴったり具合です。
また、出版元の岩波書店は日本の児童書出版社の中でも長い歴史を持つ会社。
「ひとまねこざる」や「ちいさいおうち」「はなのすきなうし」などの絵本をはじめとして、
何年たっても色褪せない、良い内容の、分かりやすい装丁の本を何冊も出しています。
けれどこうした老舗に限らず、長年読み継がれている絵本や児童書には、
丈夫に綺麗に丁寧に、大切に作られたものが多いなぁ。と感じます。
それはきっと、長い年月が経ち、時代や子どもを取り巻く環境が変わっても、
本を作る大人たちの、「子どもたちに、心に残る素敵な本を届けたい」という想いが
変わらず受け継がれ、しっかり引き継がれているからなのかもしれません。
それは、かつて子どもだった、今は大人になった、子どもとの縁が遠のいた私にも、
とても嬉しくて、幸せで、ずっと応援していきたい願いであり、望みであり、思いです。
今後もこの本が版を重ね続け、多くの子供達に読まれ続けていきますように。
備 考
原題 : Die unendliche Geschichte
エンデ,M.(ミヒャエル) , ウエダ マニコ , サトウ マリコ
ハテシナイモノガタリ
データが飛んでしまったので、この記事のみ大半を書き直して再公開しています。
いろんなことがあった春も落ち着き、しばらくぶりにブログを更新することになってみて、
ふと、このブログのタイトルを、エンデの物語の中の「あるカメ」に捧げたくなりました。
彼女の言葉と存在は、初めてであった頃から折に触れ、しばしばわたしを支えてくれます。
これまでも、多分、これからも。数々の大切な本との出会い、そのもののように。
――Heisse Keine Angst.
サキノコトハ、ワカリマス。
アトノコトハ、カンガエマセン!
きっぱりとそう「言った」カシオペイアが、今でもとても、大好きです。
 top
top  All title list
All title list 更新情報(twitter)
更新情報(twitter) RSS 2.0
RSS 2.0